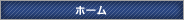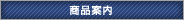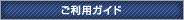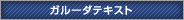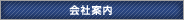インストラクター
小学2年生の頃、テレフォン・インストラクターなるものをやっていた。「8才」というと少し早熟な感じもするが、そのハンデを乗り越えるほどの技術はしっかりと身につけていたのである。もちろん仕事と遊びを一緒くたにする事などはありえなかった。好きな仕事という訳ではなかったが、その業務に対して実に真面目に務めていたのである。
テレフォン・インストラクターとは、よくある「電話でサポート」系のものではない。自宅に客を招き入れ、そのまんま「電話の使い方」を説明するという仕事なのだ。
ダイヤル式の電話を使用した事があるだろうか?円上に配置された10個の穴に指を通し、指定された位置まで回して電話をかける物である。この10個の穴にはそれぞれ1から0までの数字が振り分けられており、電話番号の順番通りその数字を回していくのだ。
その電話は私の家にあった。
俗に言う黒電話(うちの電話は緑色だったが。)だ。幼い頃から留守番の任務に徹していた私は、事ある事にその電話を使用した。小学2年生ともなるともうプロの域に達していたのである。
そんななかテレフォン・インストラクターの初仕事が舞い込んできた。
客は同い年の女の子だった。いわゆるクラスメートというヤツである。彼女は始め、私の部屋で大人しく絵などを描きながら遊んでいたのだが、不意に「家に電話する」と言い出した。そこで私は親切にも電話の前まで案内し、彼女に受話器を渡したのである。私にとってこれはなんて事もない自然な行動だった。しかし彼女は電話を前に完全に面食らっていたのだ。
「・・・これ、どうやって使うん?」
聞けば彼女はプッシュホンなどという軟弱な電話しか使った事がないと言う。
私は何食わぬ顔で初仕事をやってのけた。今までの練習の成果と少しばかり多く持った度胸でやり抜いたのだ。彼女もうんうん頷きながら、最終的に「自分でやってみる」と言ってくれた。友の独り立ちとは少し寂しい物ではあるが、私はそれを優しく見守る事にした。
ジィィィィコォォォォ(注:ジィが回す音、コォが戻る音)。
プルルルルン・・・、どうやらかかったようである。友達も少し嬉しそうだ。この表情を見る時、この仕事をやってて良かったなと思える。
着信音がしばらく鳴ったのち、相手が電話を取ったようである。友達は緊張の面持ちで言う。
「あ、ごめんなさい。まちがえました。」
・・・何故?
私の初仕事はあっさり失敗に終わった。
当サイトのコンテンツはフィクションです。文字や画像等の無断使用・転載はご遠慮下さい
Copyright© ガルーダ健康食品 All Rights Reserved.